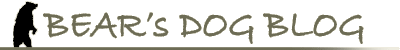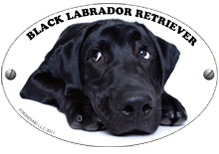National Geographic Channelで「 Dog Whisperer (ザ・カリスマ ドッグトレーナー 犬の気持ち、わかります) 」をご覧になっている方も少なくないだろう。wwwを検索すると、 シーザー・ミラン氏 の著書「あなたの犬は幸せですか」についての否定的意見が出て来るが…
番組を見ていれば、そんな意見は持ちづらい。もちろん、番組に映ってない、彼が失敗するケースもあるらしいが、氏はそれについても番組中で時折正直に触れておられる。私は、その否定意見に納得が行かず、昔、NHK BSでの放送が打ち切られたなどという事態を聞き及ぶに至っては、とても残念に思うのだ。
否定意見の最たるものは、「群れの論理」(PackやAlpha Wolf)が否定されているというもの。ところが、実際調べてみたところ、まるごと否定されているのではなく、「雄の」アルファ狼が群れを率いるという部分のみが否定されている論や、犬の調教にこの理論を適用することまで否定してはいないなど、様々。決して、Thomas J. DanielsとMarc Bekoffの論文“Population and social biology of free-ranging dogs”がそのまま認められているのではない。学説であるからには、反論・反証も当然ながら、あるわけだ。
現代社会においてフィールドリサーチが行われている以上、野犬が群れをなして暮らせる社会でないという背景も、十分に考慮せねばならないだろうと思う。多頭飼いする人は少なかろう昨今、群れとしての犬を捉える機会もまた、少なかろう。
いずれにしても、シーザー・ミラン氏が唱えているような意味での「群れとそのリーダーという概念」は、私が調べた範囲では、頭ごなしに否定されていはいないし、犬を調教訓練する上では、そうした考え方を使うことも、既にそれが普及し過ぎた考え方であり理解され易いということもあり、許容されているように見受けられた。
同書に対しては、「DNAに刻まれた」(原著ではThe concept of a "pack" is ingrained in your dog's DNA)や「飼い主のエネルギー」といった表現を、文字通り受け取ってしまった反論もあるようだ。「DNAに刻まれている」は「本能の奥深くに根ざした」というような言い回しと同じ。エネルギーは、「気」として宗教で信じておられる方もあるのだが、醸し出す雰囲気と言い換えても良いだろう。別に、科学的に論証しているわけではなく、犬とうまくやっていく要領を、ミラン氏なりの言葉で表現されているだけのことだと、私は理解した。
氏の著書「あなたの犬は幸せですか」は、National Geographic TVで放映が続いているせいか、時として安い古本は売り切れて、1680円だった本が2000円近い価格になっていたりする。だが、私は、例えそれでも手に入れる価値はあると思う。アメリカではニューヨークタイムズから新著も出てベストセラー入りしていたようだが、邦訳出版されないのはBSと、その放送に苦情殺到したとかで、関係者が懲りたせいだろうか。
シーザー・ミラン氏は、IACP─国際犬専門家協会からも認められたトレーナーである。そして、日本でIACPにつながっている組織や個人は、少なくともざっと検索した範囲では多くない様子。そんなところから、BSが放送をさっさと止めてしまったのなど、どぉも既出の訓練に相容れない面もあるであろうシーザー・ミラン氏のやり方が、かなり反感を持たれたのではないかと思ったりもする。
しかし、そのやり方は、実際、有効。自分の愛犬カブや、例えば、その自信を持って接するという部分をカブのトモダチ犬に試しても即効性があり、私自身驚いた。良く聞く「訓練所に入れて、訓練士の言うことは聞くようになったのに、帰宅したら元の木阿弥」という話も、シーザー・ミラン氏の論と併せてみると納得できる。「飼い主にリーダーとしての自信がなければ、犬は自分がこの群れを率いねばと思ってしまう」とか、「コマンドが正確でない」とか、或いは「不規則な生活と運動不足でストレスが溜まっている」といったところなのではないだろうか。
特に、散歩の量については、そう。我が愛犬Cubの散歩量は決してまだ十分だとは思っていないが、それでも精一杯の量。一日三回、三時間前後は費やすその量に対して、良くある飼い方の本などの説が30分や1時間程度なのは、いかにも少ない。増して、庭が広いから大丈夫だなんてことは、全くない。「あなたの犬は幸せですか」にも、それはただの大きな犬小屋に過ぎないとあり、とにかく疲れさせることが秘訣として繰り返し述べられている。実際、あれほど繰り返し多くのケースに触れ、日々数十頭の群れを自ら養っている実績があればこそ、各国で評価されているのだろう。「学ぶべきは学ぶべし・倣うべきは倣うべし」(納得できる部分、合意できる部分、自分の犬に当てはまる部分を採り入れる)である。
[ 続編へ → ]
[参考]
IACPに参加する犬専門家には、ニュースケートの修道士 ・ Bill Campbell氏 ・ 獣医Ian Dunbar氏 ・ 訓練士Brian Kilcommons氏 等など、テレビなどで見かけたり、良く知られていたりの方々が名を連ねている。
Posted by nankyokuguma at 18:06:11. Filed under: 躾など