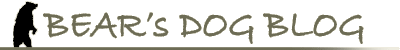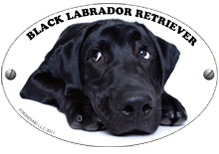継続して調べて居たら、どうやら放映された元のアメリカでも、ネット上でも然りで、未だに論争は続いているようす。それにしても…
犬も飼い主も千差万別で、一つの訓練方法が全ての犬に当てはまりもしないんじゃないか。増して、問題行動の矯正ともなれば、なおさら。残る途は安楽死しかない問題行動の重なった犬の矯正という特殊ケースが、かなり。悲しいかな、他の訓練士は彼のような手段を取らずに成功していると言われたところで、安楽死の途を辿らされる犬がいなくなったとは聞かない。一方、番組で紹介されている幾つかの例がその後継続的に成功しているなら、シーザー・ミラン氏は確かに、そうした犬の一部は救い得ている。その成功が100%でないこともまた、番組中や終わりに、氏の口から述べられている。
問題行動を矯正する番組は、海外の番組ばかりだけど、他にもある。Animal Planetのヴィクトリア・スティルウェル女史の「ヴィクトリア流 犬のしつけ教室」やアンドレ・アーデン女史の番組など。スパルタキャンプで、飼い主と同時に鍛えるって番組もあった。これらに一環して共通しているのが「十分な運動」「正確なコマンド」「毅然とした(自信ある)態度」といったキーワードと共に、飼い主が一緒にカウンセリングを受けている点。訓練士に任せれば犬が見違えるようになって帰ってくる、なんて番組は、たぶん、皆無ではないだろうか。
どう考えても、最も長い時間を犬と共に過ごさねばならないのは、飼い主。飼い主自身が自分で知識なりを身につけ、犬とうまく暮らせるように、抱える問題を解決する ─ そんな観点が、今、一番求められているように思う。シーザー・ミラン氏なりのやり方も、そうした設定で、彼なりの理解方法なり躾け方を実践して見せている、様々な番組のうちの一つ。日本では、番組そのものではなくて、 鉄腕ダッシュのダメ犬デブ犬克服大作戦 くらいだろうか。でも、飼い主と犬がペアで参加する犬のしつけ方教室は、それを併設したDIYショップやら、ボランティア団体やらのお陰で、増えていると思う。
「著名な大学教授がなにごとかを間違いなく正しいと言ったなら、翌日にはそれが間違いだと証明される確立が高い」
とは、アーサー・C・クラーク博士の言葉。飼い主の立場では、科学論争は科学者に任せて、ひたすら、愛犬と楽しく過すのが良いんじゃないかなぁ。その昔、シェパードを飼っていたのは30年前。カブが来てからあれこれ勉強しなおしてみると、まぁ新たな見識学説が、一杯。だけど、犬そのものが変わっているわけじゃなし、人が犬と接するための背景となる予備知識だけが、変わった。だから、一つの説に振り回されず、一緒に楽しく暮らせるように、良いところ、有効なところを採って行けば良いんじゃないの、と。
ある理論が科学的に正しくても、現実の訓練の方法の一つとして、たまたまその犬の場合だったとしても、非科学的とさえ言われる方法が有効ってことだってあるだろう。あるいは、逆に、どんなに権威と言われるような訓練方法であっても、まるっきり駄目だった、とかね。
ところで、シーザー・ミラン氏の著書の訳本「あなたの犬は幸せですか」は、その題からしておこがましく、悪すぎたのではないかなぁ。原著は「Cesar's Way」つまり「シーザー流」で、いたって素直なのに…。ま、こんなところで、この件は「おしまい」。
しみじみ、ラブラドールという犬種
子犬の時点で基礎的な躾を怠ると、手に負えなくなりかねないと良く言われる、大型犬。ラブラドールは特に厄介で、Wikipediaはあまり引用に適さないかも知れないが、その飼育にあたっての留意点にある
- 個体差によるところが大きいが生後2年から3年未満のものは好奇心旺盛で極めて活発に動き回る。また、家具や柱などをかじったり、破壊する行動がまま見られる。力も強いため想像以上の被害にあうおそれがある。
- 活発な性格である。盲導犬や介助犬のイメージから大人しい犬と思われがちだが、それは訓練による結果である。躾を誤ると手に負えなくなる可能性もある。
- 人に対しては非常に友好的ではあるが、それが災いして年齢や性格によっては初対面の人に対し興奮が治まりにくく、(友好の意味で)じゃれて急に歩行者などに飛びつく事がある。
といった指摘は、多少なりとはいえ経験した今となっては、私には否定できない。
なにせ、手がタコだらけになるなんざぁ、問題じゃない。気がついたら家具の一部がかじられてるのも、ご愛敬。気の引けたチョーカーもまるっきり利かず、吐こうと何しようと、ひたすら、引く。引き癖を直すというマズル部分を巻くようなリードは、嫌がって装着できず。そうこうしているうちに、家内は引っ張られて怪我をし、ジーパンも裂けた。私も、危うく頭をしこたま打ちかけたことがある。幾針も縫うハメになったという話だって、聞きおよんだのは一回や二回じゃない。とある飼い主さんは「寝ている間は天使。起きたら悪魔」と形容された。それほど、ラブラドールという犬種は、一般に想像する性質と実態がかけ離れている。映画「マーリー」のやんちゃぶりこそ、普通の(?)ラブラドールかも知れない。盲導犬は、多くの候補の中から向いた個体を選出して訓練した結果なのだ。
でも、そうした悪癖に参った挙げ句犬小屋につなぎっぱなし…なんてことは、避け得るモンなら、誰でも避けたいんじゃないかな。
で、ある程度有効だったのは、「リードを上へ引く」ことと、それこそ否定意見のあるパック論に根ざした、前に出ようとしたら、左に寄り、左足を犬の前に出して止めて、「ヒクナ」。但し、ここでもCubなりの事象が。実は、紐無し脚側行進のほうが正確で、ひたすら寄り添って歩く。ところが、リードがあると、比較的自由に動いてしまう。昔、シェパードでやった時は逆で、リードありで訓練したものをリードなしの状態に反映させたのだけれど、まるっきり逆なのだ。
リードがあれば手をつないでいるのと同じ安心し、リードがないと心細いから寄り添う、という感じ。だからと言って、リードなしで散歩できるわけでもないから、弱るわけだけど。
ちょっとした、御参考
例えば、コマンド。犬が聞く音はおおよそアクセントによるところが大きいという説がある。そうすると、アクセントが二つ=フセと三つ=スワレは区別できる。でも、フセとマテは同じ二つのアクセントで、方言の混ざり具合とか他の要素もあるだろうけど、どっちだろう、ということになりかねない。で、アクセントによる説を採って、じゃあ違うアクセントのコマンドにしたらどうだ、というわけで、フセをレイダウンに変えて試したら…成功。他にも、視符を併用したり、動きを使ったりするから区別できていることもある。
買い物などのときの「マテ」も、尋ねられたことのある躾。飼い主が目をつぶると、マテのコマンドが無視されるという興味深い実験をテレビでやっていたが、さもありなん。見てないところでじっと待つのを仕込むには、トランシーバーを利用するという話を、昔、読んだことがある。これは、昔飼っていたシェパード犬がじっと待てるようになったのが、ビルの前で待たせた犬を階上の窓から時折眺め、動いたら大声で「フセ」を命じていた、その結果だったので、納得。まぁ、本当に見られているんだ、というように思ってくれない犬なら、こんな方法は利かないだろうけど…。
実は、Cubはこのマテはなぜか、最初っからできてしまった。但し、できちゃう犬に良くあるパターンだと聞くそれらしく、出来るけれども、出来具合が今一つ、甘い。逆に、覚えの悪い子は、出来たらきちんとハマってできるらしい。だから、諦めなきゃいつかきっと、できるようになる。
ダメ犬なんて、いない。さすがに人間の知能7歳相当の、その7歳の子供同様のことをやってのける犬は少ないけれど、それぞれ、その犬なりに、それ相応の賢さは持ち合わせてるように、思う。それを信じないコトには、どんな手段を使ったところで、訓練・調教したってうまく行かんのとちゃうかなぁ。…というわけで、まぁ、人様に怪我をさせたりする前に、悪癖を直したりするのは飼い主の責任、と努力してはいるのだけど。犬好きの、良い人ばかりにじゃれている間は良いけれど、そんな人ばかりじゃないからして。
トシ相応
ところで、若い活動的な犬には十分な運動が必要 ─ これは、人間の体でも一緒。年齢を重ねれば、それは「適度な」に変わるのも、おなじ。問題なのは、十分な、或いは適度な運動を与えず、体重を減食だけで調整することのように、私は思う。というのは、必要な栄養素を様々な食べ物から得るには、必須量があり、そこを減らしては健康を害するだろうから。犬の成人病が多いと見聞きするが、人間にも成人病が大きな問題であることとは、果たして無関係だろうか、と思ったりもする。だから、減らすにしても、バランス良く減らさないといけない、ということではないかなぁ。
この運動量にも色々と説があって、本当のところ、どうなんだと思っている。現状、体重と健康状態を毎月獣医さんに診てもらい、その結果と照らして今に至っているのだけど、4歳を境目に、最近、結構変わってきた気がする。
変わってきたといえば、ラブラドールの特徴なんだか何だか、Cubの頑固さに参る時がある。嫌だとなったらテコでも動かないのも、それ。こっちがリードを頑張って引っ張っれば、ついて走ってくれると思ったら、大間違い。本犬が走っている速度に、こちらが調整する。

▲獣医さんの診察台で
実は、その速度は、道草をくうせいもあるけれど平均3km/h前後で、散歩のお年寄りにも追いつけない。自転車運動でリードしていて、うっかりすると強引に引き留められることもしばしば。本犬の意志に背いて強引に動かせるほど、40kgは軽くない。まして、腰を入れて踏ん張ったら最後、石のごとく不動状態。歳をとるほど益々頑固にならんとエエんだが…。
逆に、好きなところに行くとか、何かにおいをかぎつけて追っかけるとなると、驚くほどハイパワーで俊足。これから先、歳をとると、適度に調整しないことには、行ったっきりとか、帰りは家人を呼んで車で、なんてことになりかねない。近くに犬用プールでもできてくれたら、さぞかし良いけどなぁ〜と思うこと、しきり。
4歳を過ぎてちょっとだけ、心なしかやんちゃぶりが収まったように思う。運動の成果で、ようやく体重も40kgを切って39kgと、標準体重+1kgに減った。これまでのトレーニングでできた筋肉とあわせて、健康な老犬に…なって欲しいなぁ…
Posted by nankyokuguma at 16:38:41. Filed under: 躾など