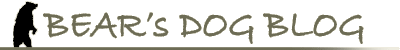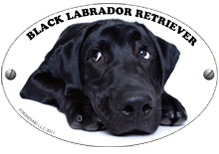犬を大きさで分けて、その性質を決めつけている向きが存外に多いので、やっぱり書いておいたほうが良さそうだ。以下、前提として、それでも個体差は大きく、あくまでも広く言われている概念的なものに過ぎないことを覚えておいて欲しい。人間を性別や出身地、身長などで決めつけられないのと同じように、犬も千差万別なのだ。
甘ったれ大型犬と、神経質な小型犬
大型犬は往々にして、甘ったれでぐうたら、気は優しくて力持ち。大きさや、目つきが威圧的だったりすると誤解されがちだが、基本的には気の優しい犬が多いとは、欧米で出会ったイヌたちをも含めた経験から。
では、なぜどう猛な印象を受ける人が少なくないか。思うに、大半の原因は、躾け損ないや、運動不足にあるのではないだろうか。犬を庭につなぎっぱなしで飼うものだとか、犬舎に入れっぱなしで大丈夫だなんて思っているなら、大間違い。庭が広いから大丈夫だろうなどというのも間違いで、おおよそ、恐らく日本の家で広いから大丈夫と言えるような「庭」(敷地ではなく、庭)はなかろう。北海道で2000坪の「庭」なんて言うなら別なんだけれど、そりゃあでも庭とは言わんでしょうよ。
一方の小型犬は、カンの強いというか、神経質というか、とかくキャンキャン吠えるのが多い気がする。犬同士で仲良くする経験が足りないとか、飼い主が犬同士がどう遊ぶものかを知らないといった原因もあるのだろうが、実はさらにもう一つ、猟犬種であれば「攻撃性を残されている」という事実が潜んでいる。多くのテリア種がそうで、意外かも知れないが、その種が求められた所以なのだから、自明。猟犬種なら、毎日8km〜12kmくらいは歩けるだろうと思う。例えダックスフントだって、数回に分けて合計5〜6kmは歩けるはずだ。そして、そうした運動量が、その犬種のそもそもの目的を達成した暮らしでの運動量なのだ。
我が家の黒ラブ、Cubの散歩は、一回で10kmを越えることもある。一日三回、合計すれば少なくてもトータル5kmを越えているはずだ。それでも、私自身は、十分足りているとは思っていない。大きな犬だからこの距離が必要なのかというと、それも違う。ある種の犬にとっては、10kmなどという距離は恐らく、距離のうちではないだろう。野山を一日中駆け回っても平気な犬種だって少なくない。ピレネー犬の優雅なほどの身軽さは、山岳地帯を飛び跳ねる能力だったりする。飼って見て分かったのは、ラブラドールは比較的運動量が少なくても済む犬種だということ。だから、盲導犬だって勤まるのだが、それでも、トータル10km前後程度は当然、必要だと思う。ローデシアン・リッジバックのようなフルマラソンを走っても平気な犬種だってあるのだし、犬橇レースでは100km/日以上を走る犬だって、いる。
犬種によりけり。大きさは無関係
もともとは猟犬種なのに愛玩犬扱いされているのが、プードル。しかし、プードルほど闊達な犬種があるだろうかというくらいで、恐らく、相当ストレスが溜まっているプードルが多いのではないかと思う。そうなる理由の一つは、ひょっとしたらペットショップが、売りたいがために必要な運動量を少なめに告げるからではないだろうか。「運動量も少なくて手間がかかりませんよ」…当の本犬にしたら、間にうけて欲しくないセールストークだろうなぁ。「いっぱい運動したいよ。手間もかけて欲しいなぁ〜」と、本音が脇から聞こえてきそうだ。
自分で走ってくれる犬 ─ ボーダーコリーなど活発で、ボールの持来なんかが大好きな犬は、工夫すればそんなに長距離を歩いたり走ったりする代わりの運動方法が採れる。一方、シェパードやラブラドールのように飼い主にベッタリが大好きな犬は、なかなかそれがやりづらく、どうしても一緒に歩く距離が伸びる。もっとも、ラブラドールは、同じ持来でも、水に飛び込ませれば楽に運動量が増やせるけど。昔、シェパードを飼っていた時の散歩は大変で、バイクを追いかけさせていた。20年以上昔のこと、某有名高級温泉旅館で主から私らとの同室泊を許されたほどだったけれど、持来だけは躾け損ねて、投げると「ご自分で投げられたもんはご自分で取ってらっしゃい」って顔をしてたなぁ…。
小型犬も、前述のように猟犬種ならば特にだが、運動量は必要。たいして要らないのは狆やスピッツなど、存外に限られる。それに、小型犬、特にテリア系は、種として狩猟本能を残して生み出された犬種だから、自ずと攻撃性がある。とある海外のテレビ番組で「子供は噛まれるから、子供のいる家庭には不向き」と紹介されていて意外だったのは、ヨークシャーテリア。これまで犬を躾けた経験がなく、子供が小さくて万一のことを考えるなら、ヨーキーだけは止めておいたほうが良いらしい。
それでなくても私は、小型のテリア系犬種は気軽にはお勧めしかねる。特にどうしてもという場合は、その分、躾け方を学ぶのに精を出す覚悟が要るだろう。例えば、存外に運動量の必要なジャックラッセルテリアも、我慢強さに欠けるので子供と遊ばせるには注意が必要と言われる。
ものの本によれば、小型犬がキャンキャン吠えるといった性質は、犬としての社会性を身につけ損なっている場合もあるようだ。8週目を基準に、それより早過ぎても遅過ぎても、親元を離れて飼い主のところに来るタイミングとしてはベストを逃すのだが、その理由の一つは、兄弟犬と過ごす経験だという。感染症予防のためにワクチンが終わるまではお散歩デビューさせなかったりするのだが、この期間を過ぎてなお犬をネコっかわいがりしていて「群れで暮らす動物としての本能」を忘れさせると、犬としての社交性が失なわれることにつながりそうだ。
庭につなぎっぱなしは最悪で、人間社会にも犬社会にも溶け込めない性格に歪める。人間がそうやってつなぎっぱなしだったらどうなるか、想像してみたら良い。犬だって同じなのだ。たまたま通りかかる人たちがやさしくしてくれていたりして、救われているケースはあるけれど、番犬に、といってもあまりに凶暴では、困る。幼犬時に大型犬を躾け損なって手に負えなくなり、庭先につなぎっぱなしというのは最悪のパターンで、悲しくなる。
ドッグランで運動させれば大丈夫というのも、誤解。ドッグランは、散歩で発散した後で行くべき先で、言わばご褒美のようなものだそうだ。発散しきった後なら、大人しく社会に溶け込める。が、ストレスが溜まったままの行動は、他の犬に受入れられにくいとは、後述するシーザー・ミラン氏の弁。
犬は群れで暮らす動物。仲間になれる犬に
犬同士は平和共存しようとするのが基本の素質だともいう。例えば、ある犬が近づいた時に目をそらすのは、「事を交える気はありませんよ」という意味。人間だって「ガンをつけた」などという、あれと一緒で、にらみ返せばケンカを売ることになる。番犬としての凶暴性は、自分の参加する社会に危害を加える可能性のある場合に発揮されれば良いのであって、仲間に牙を剥くようではいけない。群れで糧を得る犬たちの野生には、無駄な争いをする余裕など、あろうはずがない。

総じて、「犬は群れで生活する生き物」を基本に「犬同士の社会は平和主義的」なのだから、散歩で出会う犬同士は、仲良く遊べて当然なのである。但し、人間同様に相性はあるようで、これも観察していると面白い。
Cubがとても仲の良いポメラニアンは、もともと大型犬が駄目だったそうだ。偶然、Cubが体を低くして甘えた恰好を見せたら、ポメラニアンのほうが駆け寄って、上に乗るわ飛びかかるわ、大はしゃぎ。それ以来、この二頭はほぉっておくといつまでも遊んでいるようになった。(写真上)

他にも、コーギーやウェスティなど、Cubの場合は大小問わず、どんな犬種にもトモダチがいる。犬は、孤独では生きられないのだ。
犬の脳の大きさが体重に占める割合は体格によらず同じだそうで、賢いかどうかはブリーディングによりけり。だけど、殆どの犬はそれなりに「賢い」。少なくとも、馬鹿な犬なんぞはいない、と私は思っている。後先考えんのはいるけれど、それは悲しいかな人間も一緒。とにかく、上手に躾ければどんな犬だって、幸せに飼い主と、飼い主を取り巻く社会に溶け込んでいられるはずなのだ。そこに、犬の体の大小による差異など、生じる余地はなかろう … 飼い主自身が毛嫌いしなければ。
躾で成功するには、ちょっとしたコツも要る。手っ取り早く学べるテレビ番組は、例えば「Dog Whisper」。カリフォルニア在住のメキシコ系調教師シーザー・ミラン氏による、駄目犬の訓練シリーズ。邦題「ザ・カリスマ ドッグトレーナー 〜犬の気持ち、わかります〜」だろう。彼は犬よりも飼い主を重視し、飼い主に毅然とした態度をと求める。日本のナショナルジオグラフィックチャンネルでも放送している。ミラン氏の論からすれば、訓練所に犬を預けたのに戻ってきたら駄目なまま、という良く聞く話も頷ける。愛犬家 ─ いや、とにかく犬を飼ったり関係があったりする方は、必見だと思い、お勧めする次第。「シアワセな犬がもっと増えますよぉに」と、願いつつ。
Posted by nankyokuguma at 15:13:52. Filed under: 躾など