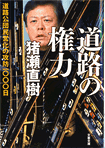溜まっていたツケは、ざっと約40兆円。自動車一台あたり50万円以上だ。よくもまぁ、これだけのツケをユーザーに回し、サービスエリアでまずい飯を食わせながら、天下り大ファミリーで私腹を肥やしてきたものだ。
猪瀬直樹氏の著書、道路の権力と道路の決着、二冊セットをようやく読み終え、先ずは、利権で醜く膨れあがっていた道路公団を民営化すべく闘い抜かれた、そのご努力に頭が下がった。40兆円を民営化して返済する計画を立て、それに沿って物事が運びだしているところまでは、よくぞやって下さいましたと思う。けれど、読後、どこかで腑に落ちない、不安のようなものがまとわりついてきた。
一つは、自動車の台数が減りだしていることに伴う需要予測の変化。当初計画は当初計画として、動き出す段階での目論見は正しいのだけれど、現実はそうした目論見を裏切りがち。高速道路の利用料金収入だって、1000円の割引が始まったがために返済にあてられる料金収入減に伴って、リース料の支払い額も減っている。そこは、もともと計画されていた利用促進のための予算枠で賄われるという話なのだし、二年限定。だったら予定通り終われば良いものを、2000円化で値上げだと言われて延長。政権が変わったとはいえ、おおよそ、計画性というものが「ない」。
だが、ここで問題なのは、そうした愚かな無計画性よりもむしろ、返済案が再び闇の中になり、なし崩し的に再び赤字垂れ流しの道路が作り続けられかねない、そうした現状ではないだろうか。そこで、改めてまた、高速道路問題を考えてみることにした。
■ 分かるが頷けない無料化論
もともと無料化案は、道路の権力・道路の決着にも出て来るのだが、民営化案に対峙して野党民主党時代に現首相の菅直人氏が担ぎ出した。これを唱えるのは、山崎養世氏や大前研一氏。山崎氏の論と大前氏の論では、たまった借金を返す仕組みが違う。山崎氏は国債として、より低利で償還。大前氏はプレート税のような新税で賄う案。シャドゥタックス化するのか、おおっぴらに徴集するのかの違いだ。
そこで山崎氏の案をWebサイトで幾度となく拝見していて、妙なことに気がついた。氏は40兆円の金利を80兆円と記されていて、合計返済額は120兆円だという。だから、より低利の国債で短期償還したほうが良い、となる。ところが、手許でどんなに計算してみても、金利は同条件なら52兆5千7百億円。返済すべきは90兆円なのだ。はて、どういう計算で倍近い金利がついたのだろうか。
さらに調べて見ると、あれこれと値下げ原資などを求めたためか、政府保証のある債券もある上、このところの傾向で、返済資金の調達はかなり低金利。こうなると、例えそれが説よりも安く済む話であっても、頭ごなしに信じて山崎論を唱えるわけには行かない。そこで、再計算。金利と期間をあれこれ変えると、料金を下げたり償還期間が短縮できるほど低金利だというのが、スプレッドシート上でも良く分かる。分かるが、返済の構図が変えられるほどではない。実際に残っているのは、着実な返済の結果、31兆円。二輪を除く自動車の数で割ると、一台あたり40万円強で、既に10万円も返済済みのようだ。
借金などというものは早期の返済に努めるのが筋だろうし、実際、これほどの低金利なら、前倒しできる限り前倒しで金利負担を軽減したほうが良いに決まっている。40年といった単位で返済を実行するために作った機構だからと、もし、何がなんでも40年かけるんだというような姿勢でいられるのだったら、返済を終えて無料になる日を夢見て現実に負担を続ける高速道路利用者の立場から見て、納得できるわけがない。それに、40年先じゃあ、私が存命のうちにはタダにはならん。
もう一人の無料化論者、大前研一氏がこの借金を「子の代に負わせるべきではない」と仰せなのには、大賛成である。しかし、同氏の言う1万円のプレート課税・ステッカー方式も、国道予算内のシャドウタックスプラス1万円という、今一つ返済計画が見えにくく、手放しで賛同しづらい案だ。
■ 高速料金一部肩代わりで税収確保?
ところで、割引の1000円と2000円、どちらも目先では週末の行楽の移動コストを減らすわけだが、自動車たるものガソリンは使う。道路特定財源は平成21年度から一般財源化されたから、2008年から「値下げのため、各高速道路会社が事実上抱える債務の一部肩代わりに、向こう十年間、道路特定財源から約二兆円を投入する」とした、その当時計画された財源は、今や一般会計だ。
「ETC限定、土休日乗用車以下、終日半額上限1000円」の財源は、財政投融資特別会計(埋蔵金)からの2兆5000億円。ガソリン高騰時に減った消費量を一般財源化した税収を維持するために持ち上げようとすると、埋蔵金の一時金2.5兆円があるから、これを活かして毎年の暫定税率込みのガソリン税収3.2兆円を確保しよう、という判断だったのだろうか。一年間の減額費用0..5兆円差し引いても、2.7兆の税収が見込まれる。
ところが、いよいよ一般財源にしようかというタイミングで、石油価格が高騰し、石油消費が落ち込んだ。政治の迷走で暫定税率は一旦切れて低価格化し、2008年の連休前に再課税された。そんな油を車にくべつづけてもらうには、高速道路の価格を下げれば良いと、福田さんの耳元で誰かが言ったのだろうか。折から、サブプライムローン問題で景気が冷え込んだため、緊急総合対策と銘打って深夜割引などを拡大した。麻生内閣ではさらに、景気対策としてこれを休日1000円など拡充。先頃まで、この割引のために調達した原資は2.6兆円残っていた。
高速道路の料金をタダにしてでも、燃料にかかる税金で総額5兆円規模を確保できるなら、辻褄は合う。つまりは、それほど走り回ってもらわないと、今や一般財源となった3兆円は入ってこないのだ。週末1000円の高速道路上でガソリンを消費している方々も、結局は渋滞を辛抱しながら税収を支えておられることになる。だが、それでも内需景気は回復しないままだ。円高で外需利益も吹き飛んでいる現在、割引の期限だった時期は見直しに妥当な頃合いだったと思える。
国土交通省が改善した将来交通需要推計にも明らかだが、交通量推計は下降線しか辿らない。昨年8月に出た中間取りまとめ結果を見ても、猪瀬氏の予測ピーク2015年〜2020年とも違い、減る一方になっている。今後、燃費の良いハイブリッドや電気など化石燃料以外で動く自動車が増えれば、自動的に石油類による税収は減る。良くなった燃費やガソリンを使わない電気自動車の利用は、見方を変えれば一種の節税行為なのだ。
自動車がこれまでのように石油を消費するのを前提にした税収を維持しようとするなら、税源を他に移さねばならない。人口が減り、自動車保有量も減る傾向にある。若者は車を持たず、全体に自動車という文明のパイは縮小傾向にある。移せる税源はどこにあるか。走行距離である。走行距離を伸ばすにはどうすれば良いか。高速道路を格安、或いはタダにすれば良い。
■ 税収確保の難しさ
だが、事はそう単純には行かない。例えば、走行距離課税制度を採るとなると、走らずに節税しようとする傾向が出て来る可能性がある。ガソリンはくべないと車が走らない、走らなければ車の意味がないから、嫌でも使うし、少しづつだからあまり意識しない。それが、タクシーのように距離相応に税金が上がると、嫌でも意識する。こうなると、走行距離課税では目論見が達成できない。
登録ベースの四輪車数総計は75,260,350台。計算してみると、菅総理がボソッと言ったという「一台5万円の税で…」は、高速道路会社の借金返済と現在の高速道路利用料金にガソリン税も足して、ざっくり台数で割って10年で支払うとした場合に辻褄する数字。ガソリンを無税にしても、走行距離税で平均一台5万円に相当する金額の徴集が可能ならば、という、取らぬ狸の皮算用。
もし、これを全否定して、鉄道や船舶にある環境面でのアドバンテージを優先するならば、既に一般財源化してしまった今、ガソリン税に見合った額の税金を両者から徴税せねば、車が減って発生する税収減を補えない。しかし、人間に「移動税」をかけるなんて、あり得ない。CO2は減るからそれをオフセット額と看做せば辻褄する、とでも考えるしかないが、残念ながら排出権取引で車に乗るか乗らないかの取引額差は、Yahoo!カーボンオフセットの自動車に乗る・乗らないの差でみても、ガソリン税のそれに及ばない。結局、脱自動車が進んでしまったら、税収が大きく減ることになる。何をするにも資金は必要だから、やはり、どうすれば今の税収枠が極端に縮小しないで済むかを考えないといけない。
■ 低金利を活かして返済計画を見直せ
民主党は残りの2.6兆円をさらにいじくりまわして、割引財源を必要な道路の建設に転用するのだが、それも、自動車を有効に使える利便性の確保。成り立ちをこれまで延べてきたように分解すると、やるべきことは見えてくる。1000円が2000円で実質値上げだというが、根本的には割引であり、マニュフェストの呪縛で諦めきれず、無料化の方向性を示している。
だが、もし仮に、31兆円、金利1.2%の高速道路国債を国が15年償還で出して受け入れられたとすれば、年におよそ2.3兆づつ返せば借金は消える。金利1.2%は、今時の債券としてはそう悪い金利ではない。親方日の丸格付けAAAの高速道路会社の発行している債券の金利は、もっと低い。だから、無料化論のうち、今の借金を肩代わりさせて一旦そこで決着をつけるというのは、決して悪い案ではなかろう。金利の節約分は膨大な額になる。
タイミングとして、日銀による長期国債の大幅買い増しが提唱される今は、絶好の機会だ。償還原資は、一般会計で担う。燃料と走行距離やその他の要素で税の負担を分散させ、油といわず電気といわず、或いは上を通る荷物や自転車など、とにかく道を使うものからは、適宜分散して妥当な税を取る。この方法はエネルギーの代替進捗に応じて柔軟に考慮して行く。こうしないと、前述のように通行料金や原油価格などの変動要素から利用量の見込みが外れかねず、あまりに長期の返済計画では、現状に鑑みて破綻が懸念される。それに、暫定税率を一般財源化したのだから、暫定税率ありきで発生したツケも一般財源で見て貰うべきだ。
こうすれば、借金返済がなくなり、通行料金の無料化も視野に入る。だが、タダほど高いものはない。
■ 無料化はしないが、徹底的に値下げ。
そもそも、タダで道路が維持管理できるわけがない。穴だらけの高速道路は一般道路とは違って、大事故に直結する。昔、一時期経済の脆弱化したアメリカのフリーウェイを走っていて、路肩に止まった故障車両が非常に多かった経験がある。キャンプ旅行をしていた私たち家族が乗っていた車も、途中で予定外に一泊。あらゆるネジの増し締めが必要になった。それほど、穴だらけだったのだ。ニューヨークなどは、高架道路が危険で閉鎖されていた時期があったのをご記憶の方もあるだろう。日本の道路が、そんなことになって良い筈がない。
やはり、価値に見合った必要な料金は頂戴するのが良い。上限を2〜3千円として、料金距離推移カーブをU字型、利用者の多い距離で安く上がるように設定してはどうか。利用者が適量増えれば走行距離は保たれ、現在燃料によっている税収も、上手な新しい課税方法を探る間、とりあえずは維持されやすいのではないだろうか。料金が下がれば、クレジットカードを作れない方も利用可能なETCパーソナルカードの、今は高額なデポジットも下げられる。週末に限定した偏った割引でなければ、通行量も分散されるから、駄賃を払うに見合った「高速」道路たり得そうだ。
ちなみに、道路運営会社は週末1000円割引下でも1.4兆円の道路リース料を保有・債務返済機構へ支払っている。
■ 民営会社を存続し、未来へ
肩代わりと同時に日本高速道路保有・債務返済機構を廃止するかと言えば、否。利権漬けの、あの悪夢の無責任構造に戻せるわけがない。ここは、折角組織ができているのだから、廃止せずにそのまま道路事業を続けてもらうべきだ。メンテナンスは不可欠だし、新たなシステムを構築する社会実験を行う原資も要るだろう。うまく回っているシステムは変えるべからず、だ。
債務返済機構には、現在の新技術開発などの面を引き続き担って貰う。ちょうど、JRにとっての鉄道総合研究所である。リニアをJRが国によらず独自で敷くと言い出していることなど、民間で進めたほうが物事が早い好例である。道を所有するのは、現状通りで債務返済機構。道を借り受けて事業を進める高速道路株式会社には、借金がなくなった上でのかなり低額の道路リース料を、最低限の有料道路通行料収入やパーキングエリア営業の賃貸料などで納めて貰うとともに、道路の管理運営実務を担って貰う。だから、相当安くなるとしても、完全無料にはできない。
但し、完全無料化案同様、乗り降りするインターチェンジは幾つも作り、課金するETCのポイントは別な場所、嫌でも通る区間内に設置する(実際、現在でも既にそうなっている箇所はある)。ETCをインターチェンジに備えないのは、設置に二億円もかかるというETCにたよっていたら、インターチェンジが増やせないからだ。ただし、既に設置されている、出たところで減算する方向のETCデバイスでも良いし、或いは、もっと簡便な方法を探り、ETCであっても二億円もかけずに設置できるようにするのも良いだろう。
■■■
民営化そのものは、膨大な借金を返済する仕組みを整えたのだから、価値はあった。今は、その後5年を経てこれからどうするかの岐路だ。
自動車とそれを取り巻く環境は、小泉内閣の頃に考えられていたよりも、遙かに早いペースで変貌しだしている。インフォモビリティや環境策を織り込んだ新しい道路と、その道路を走る新しい自動車で織りなされる未来が迫っているのである。明るい未来システムをこの国で実現し、自動車と道のセットで、それを世界に売る。そんなビジョン実現のための費用を含む高速道路料金なら、利用者が払う時の気持ちも明るかろう。
つけなくてはいけないのは、我田引水の道路のための予算のツバではなく、そうした道筋。それでこそ文字通り、筋が通るというものではないだろうか。
参考・出典
- 平成22年5月末現在 自動車保有台数 http://www.airia.or.jp/number/index.html
- 山崎養世氏 日本列島快走論 http://www.yamazaki-online.jp/kaisoron/gaiyo/
- 高速道路無料化の“内容”を理解出来ない政治家 http://blog.goo.ne.jp/ohmaelive/e/b610634222900f768b985b54a1ef17d7
産業突然死時代の人生論 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/60/index2.html (プレート税案) - Yahoo!カーボンオフセット http://carbonoffset.yahoo.co.jp/
- 日銀による長期国債の買い増し 日本経済新聞8月21日土曜日朝刊1面「成長鈍化いま何が必要か 5」野村証券チーフエコノミスト木内登英氏 http://www.nikkei.com/ (会員向)
- 独立行政法人 日本高速道路保有機構・債務返済機構 平成21事業年度財務諸表等 http://www.jehdra.go.jp/zaimu21.html
- 国土交通省「将来交通需要推計の改善について【中間取りまとめ】」について http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo11_hh_000004.html
Posted by nankyokuguma at 14:28:48. Filed under: Vehicle